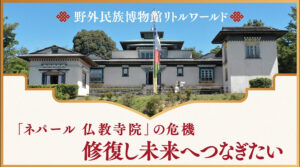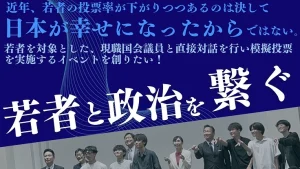私たちの住んでいる愛媛県西予市宇和町皆田は山に囲まれた小さな盆地です。この地域の中心にある水田が今、耕作放棄地になりそうな危機を迎えています。理由は「人手不足」と「稲作の収益の低さ」と「農道や水路などインフラの劣化」です。それでも住んでいる地域を守り、先人が守ってきた農地を受け継ぎたい。そこで水田の一部を果樹園に変え収益を改善することで農道や水路の改修をしようと考えています。
水田を果樹園にするためには、苗木を植え、棚を張り、雨よけハウスを作り、潅水設備を作り…とたくさんの作業や投資をする必要があります。しかし今の会社の収益でそのすべてを行うことは困難です。この費用の一部をクラウドファンディングで補いたくプロジェクトを立ち上げました。
この新しく作る果樹園では、手間をかけすぎない果実の生産に取り組むことを計画しています。そうすることで形は悪くなりますが、見た目の美しさよりも、おいしさやお買い求めやすい価格を実現することができるからです。
「これからも本物の果実があなたの身近にありますように」これが私たちの願いです。
自己紹介
この度は数ある中から、私たちのプロジェクトに目を留めてくださり、ありがとうございます。
はじめまして、(株)りの果樹園 代表取締役 松本 弥生です。
私たちは愛媛県西予市宇和町でブドウ1.7ヘクタールとイチゴ30アールを経営の柱に、水稲2.5ヘクタール、キウイ40アールを栽培しています。法人化して3年目のまだ足元の覚束ない会社ですが、スタッフは私を含めて6名です。20代から60代の農業では比較的若いといわれるスタッフたちで、日々農園で奮闘しています。





▲りの果樹園スタッフ一同
農業=地域の問題について考えること
現在、農業は3つの問題に直面しています。それは、1:人手不足、2:収益性の低さ、3:農地保全の難しさ、です。
日本の農業経営のうち家族経営体が占める割合はとても高く、2020年のデータでは約96%(出典:農林業センサス)を占めています。
家族経営が多い理由は様々でしょうが、家族経営から始めた私が感じることは、一つの作物を生産する経営では農繁期と農閑期があり一年を通じた雇用が難しいこと、そして定められた最低賃金を払う収益力が確保できないからだろう…ということです。
労働の大変さにとても見合わない収入の少なさから、大切に育てた子供に「農業を継いでくれ」とは言えず、都会に出てゆく子供たちを見送った親は日本中に数多くいるのではないでしょうか。
私たちの地域でも20代30代の人口は減少の一途です。なんだか地域がスカスカしてくるのを肌で感じます。そうして毎年のように高齢になった生産者から、「農地を引き継いでくれ」と言う声が私たちにかかります。ここはとても無理!という山の斜面から、誰かがやらなければ近隣の農地までが荒れてしまう…という農地までさまざまです。
しかし、ここだけは荒らしてはいけないと感じる農地があります。それは地域の集落と集落の中心にある水田です。ここが耕作放棄地になってしまったら、地域全体が放棄されてしまったような土地になると感じています。

▲山に囲まれた盆地の中心に広がる水田
プロジェクト立ち上げの背景
2024年の春、1.5ヘクタールの水田を管理していたご老人が亡くなりました。そこから急遽、私たちに「なんとかその水田を作ってくれないか」と声がかかります。誰かがやらなければ1.5ヘクタールが耕作放棄地になってしまうとの思いは私たちも同じで断り切れず引き受けました。それが苦難の連続になるとも知らず…
もともと水稲を1ヘクタールほど作ってはいたものの赤字ギリギリの収益なので、トラクターや田植機、コンバインも年代物な上に小型なものしか所有していません。倍の2.5ヘクタールとなると、まずトラクターが壊れました。(農機具屋さんを呼んで修理しました)それから水路の石垣が崩れ農道が壊れていたので、トラックのタイヤが溝に落ちました。(みんなで引き上げました)田植機も4条植えなのでスピードが遅く、最初と最後で植えた苗の生育が違うことになりました。そのうえ2024年の夏は雨が降らなかった上に、水路から水が回ってこなかったので水田の水が干上がってしまい、水をポンプアップしてしのがなければなりませんでした。
水が回ってこなかったのは各水路の掃除がおざなりだったり、コンクリートが割れていたり、モグラの穴があったりと理由は様々ですが、ここでも人手不足と収益の低さからくる大型機械への投資の躊躇や農地保全の難しさをひしひしと感じました。
結局、引き受けた水田ではまともな収穫すらできないありさまでした。

▲数カ所ある農道横の壊れかけた水路
▲機械が小型な上、水田も区割りが細かいのでなかなか進まない作業
▲溝のメンテナンス作業も人力
何としても農地を残し、未来へバトンをつなぎたい…
一般的には、10アール当たり約540キロのコメが収穫できると言われています。しかしこの地域の水田は砂地なので収穫量は少なくおおよそ420キロになります。2024年の農協の買取価格は30キロ7500円。単純計算では10アール当たり10万5千円の売上になりますが、そこから肥料代・苗代・水利費・人件費・機械の償却費や修理費などを引いていくと2~ 3万しか利益が残りません。この利益では農道や水路の修理代を捻出することは不可能ですし、大型機械の導入も厳しいという状況です。
しかし、どうしてもここを農地として残したい!という思いだけは捨て切れません。生まれ育った地域であり、子供たちが育っている地域でもあるからです。先人から受け取ったバトンを何としても未来につないでいきたいのです。
水田を果樹園へ!会社設立3年目のやや無謀な挑戦
農地を残すためにりの果樹園になにができるだろうか...それを悩み抜いた結果、出てきた答えは水田を一部果樹園に変えていくということでした。
作る作物や生産者の技術にもよりますが、ブドウなどは10アール当たりの売上が100万円を超えます。これなら利益から農道の整備費用や効率化を図るための機械の取得費用をまかなうことができます。
そして水田を果樹園に変えていくということは、法人化し、20代から40代までのスタッフを抱える私達だから出来る事だとも考えています。果樹を生産するには長い年月がかかります。まず苗木から成木になるまで約5年。この間は必要な管理に対し満足な売上は得られません。新人が一人前に仕事をまわせるようになるまでも、やはり5年はかかります。果樹は1年に1度しか一通りの作業を経験することができないからです。家業による経営であれば、たった一人の思わぬ事故や病気で経営を続けることが困難になります。そして限られた人数で仕事を回していくため、作物の多品目化や経営面積の拡大にもなかなか歩を進められません。
しかし株式会社であれば、個人経営よりも人が集まりやすく、複数のスタッフで経営を回していくことができます。年間を通じた作業を作るためにも作物の多品目化が必須になり、経営面積の拡大も可能になってきます。
また人材の流動化も起こしやすいです。農業を志す人の家業が農業でなかった場合でも、株式会社に入社することで社会保険の対象になりながら一人前の農業者を目指すことができます。
とはいえ、これが無謀な挑戦であることは私たちが一番よくわかっています。会社設立3年目のまだまだ作業に不慣れなスタッフも多い中で日々の作業をこなしながら時間を作って果樹園を整備することも、天候の変化や資材の価格上昇など先読みできない要因を抱えながら資金を果樹園の整備に回すことも、リスクに見合わない賭けを始めることに違いありません。
やめておいたほうがいいのではないか…どうして私たちだけが地域の問題を背負わなければいけないのか…そう思う気持ちはあります。
しかし、時の流れを生き抜き現在に受け継がれたものは、誰かが歯を食いしばり守ったからこそ残って、今を生きる私たちに恩恵を与えていることも実感として分かるのです。
だからこそ次の世代にバトンを繋げなければならないと。
新しい果樹園で挑戦したいこと
果樹園を軌道に乗せるために、苗木を育て成木にするまで5年かかると書きました。なのでスタートは早ければ早いほど良いと考えます。1年先延ばしにすれば私たちも1年歳を取ってしまうからです。そこで愛媛県試験場の先生と相談の上、キウイ・ブドウ・ナシ・モモの苗木を植えました。キウイ20アール、ブドウ10アール、モモ4アール、ナシ6アールです。
農閑期にできるだけ果樹園を整備したかったのですが、2025年現在、時間的な制約と金銭的な制約によりまだまだやらなければならない作業が残っています。先を急ぎすぎたかな…と少し反省もしています。