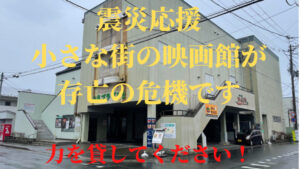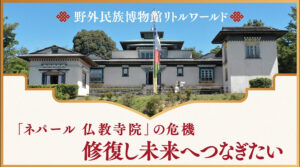無医島の人々に医療の光を
海をわたる病院「済生丸」
瀬戸内海には700余りの島が点在しています。国内唯一の診療船*「済生丸」が活動している岡山、広島、香川、愛媛県には有人島が84島あり、そのうち医療機関のある島は39島で、充実した医療を受けられる島はわずかとなります。そのため、病気の発見や治療が遅れる人も多いのです。
済生丸は、これまで半世紀を超える長きにわたり、瀬戸内海の約60の島々を巡回し、島嶼(とうしょ)部の方々の診療・検診を行い「海をわたる病院」として親しまれてきました。これまでの総航走距離は918,883.66㎞(地球約23周分)、受診延人員は627,441人にもおよびます。
しかし現在、診療に不可欠なX線機器の老朽化が進み、2025年12月までに機器を更新しなければなりません。正確な診断を維持し、離島の人々に適切な医療を提供し続けるために、今回、機器更新の実現を目指してクラウドファンディングに挑戦します。
離島の人々が安心して暮らせる医療環境を守りたい──。医療機器の更新とサービスの強化により、さらに多くの島民の方々に必要な医療を提供し続けるために、皆さまの温かいご支援をどうかよろしくお願いします。
* 定期的に巡回診療を行う船として国内唯一の診療船「済生丸」

医療を乗せて走る船
60余年の軌跡といま
済生丸の歴史は1961年(昭和36年)、初代となる「一世号」の就航から始まりました。当時の岡山済生会(総合)病院 院長の大和人士先生の発案により、医療環境が十分でない離島の人々が安心して暮らせるよう、診療活動が展開されました。その根底には、「治療から予防へ」という理念があり、島の医療を実践することで、予防医学の普及を目指すという強い信念が込められていました。
船の歴史は改造一世号、二世号、三世号と続き、2014年(平成26年)に就航した四世号(現船)は、国と関連4県の支援を受けて完成しました。済生会創立100周年に建造を決定したことから通称「済生丸100」とも呼ばれています。
船体構造は、これまでの運航で蓄積したノウハウを生かすため三世号を基本とした設計で、全長33メートル、型幅7メートル、満載喫水2メートル、総トン数180トン、航海速力は12.3ノット。
瀬戸内海における医療の発展を目指し、済生丸は就航以来、「自らの健康は自ら守る」という予防医学の理念を掲げてきました。地域の保健活動を充実させるとともに、医療や福祉の向上に貢献することを使命とし、一年間を通して定期的に、四県の瀬戸内海の島々を巡回しながら診療を続けています。
船内の通路を車いすが通れるように広くし、エレベーターを設置するなどバリアフリー化。そのほか、X線装置をすべてデジタル化し、新たに乳房撮影装置を導入するなど、中規模病院並みの診療機能を備えています。また、船体、機関および電気の各部門にわたり装備の充実も図られています。

現在、瀬戸内海巡回診療事業(以下、済生丸事業)は、四県の済生会支部が共同で運営しており、関係自治体や住民の要望も踏まえて年度開始前に年間計画を立て、約10日ごとに各県を巡回しています。
航行する距離などにもよりますが、おおむね早朝に停泊港を出発し、島に到着します。午前中に診療・検診を行い、終了後、停泊港に向けて出発し、昼過ぎから夕方には帰港するというスケジュールです。行き先によって宿泊を要することもあります。

限られた医療の中で暮らす
島民の命を守るために
済生丸の運航・管理体制は、船長以下5名の船員があたっています。診療・検診には、関係四県にある済生会の8つの病院からスタッフが持ち回りで乗り込み活動しています。スタッフは診療・検診の内容によって4~12名程度、職種は医師・薬剤師・保健師・看護師・放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・栄養士・MSW(医療ソーシャルワーカー)・事務職員と多岐にわたります。
済生丸では、船内に備えられた医療機器を活用した診療や検診を行うだけでなく、公民館などの地域施設を利用した健康教室や栄養相談等も開かれています。島民の方々が積極的に参加し、健康維持への関心を深めています。
それだけでなく、済生丸は 島々の人々が集い、語らい、支え合う場でもあります。診療の合間に交わされる何気ない会話、検診の帰り道に生まれる温かな笑顔。この船が訪れる日は、単なる診療の日ではなく、 暮らしに根ざした文化のひとつとなっています。医療を通じてつながる絆、励まし合う心の交流が、済生丸を「人と人を結ぶ船」としても機能させているのです。